
ビジネスを労務面と財務面から支援!知っておきたい社労士にできる10の業務

社労士にできる10の業務
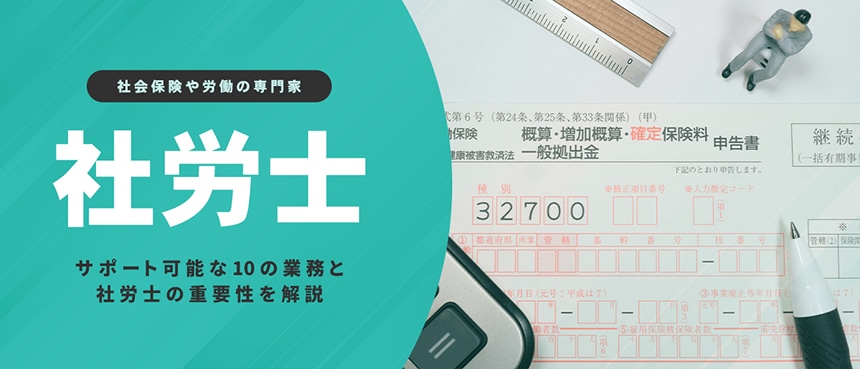
社労士(社会保険労務士)は、労働・社会保険に関する専門知識を持ち、企業や個人の労務管理をサポートする国家資格者です。
社労士ができる業務の領域は非常に多く、企業の健全な成長には欠かせない存在と言っても過言ではありません。
創業してまもないベンチャー企業の経営者などは、社労士の必要性や顧問契約を結ぶメリットを知ることから始めましょう。
具体的に社労士がどのような業務を行えるのか、代表的な10の業務をご紹介します。
①労働社会保険の手続き代行

健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などの各種社会保険の加入・喪失手続きや、各種届出の代行が社労士の代表的な業務です。
社会保険の手続きを適切に行わなかった場合、企業や経営者が罰せられる恐れもあります。
労働社会保険の各種手続きは複雑なルールがあるため、専門家に任せた方が安全で時間も掛かりません。
算定基礎届や確定申告といった定期的な手続きもあるため、いつでも相談できる社労士を見つけておくことをおすすめします。
②就業規則の作成・見直し
労働基準法や労働契約法に基づき、企業の就業規則の作成や見直しをサポートしてくれます。
適切な就業規則は、労働トラブルの未然防止や労働環境の整備において必要不可欠です。
昨今は労働基準法違反に対する取り締まりが強化されているほか、法令遵守を徹底しない企業はインターネット上の口コミなどで悪評が広まるリスクが高まっています。
また、就業規則を作成した後も従業員からの要望や状況の変化に応じて、見直しを検討する場面は意外に多いものです。
こうした際に会社の実情を理解している社労士のサポートがあると的確なアドバイスを受けられるため、安心して労務管理を進めることができます。

労働時間の適正管理や柔軟な働き方の導入支援、テレワーク導入支援なども社労士の業務です。
様々な企業の労務環境を見ている専門家ですので、働き方を見直したい場合は気軽に相談してみてください。
③財務関連業務
賃金台帳の作成や記帳代行などの財務関連業務は、一般的に会計士や税理士、または経理担当者の業務とされていますが、社労士も労務管理に関わる範囲で賃金台帳の作成や労働保険・社会保険の手続きに関する書類作成をサポートすることがあります。
特に労務に関する法令遵守や労働条件の整備に関わる部分については、社労士がアドバイスやサポートを行うケースが多く見られます。
なお、記帳や会計処理そのものの代行は一般的には会計士や税理士の業務範囲となるため、必要に応じて財務関連業務の専門家と連携することが望ましいです。
企業の資金繰りに関する部分は、金融の専門家や弁護士に相談するのが理想です。
しかし、中小企業は社労士や税理士のみと顧問契約を結んでいるケースが多く、専門家への有償相談には消極的な経営者も少なくありません。
労務管理や従業員の雇用維持に関する相談と併せて、社労士から総合的な経営サポートを受けることが可能です。
一例としてファクタリングなど銀行法・貸金業法に該当しない方法で資金調達する場合、契約内容や条件について法的な観点や労働法規に抵触しないかどうかのアドバイスを求めることができます。
参考サイト▼
ファクタリング会社を一覧から探す
資金繰りが労働者の権利や会社の法令遵守に影響を与える場合があり、社労士から助言を受けることは非常に有益です。
社労士は経理や資金繰りのスペシャリストではないですが、財務関連業務の分野でも役に立つケースがあります。
④補助金・助成金
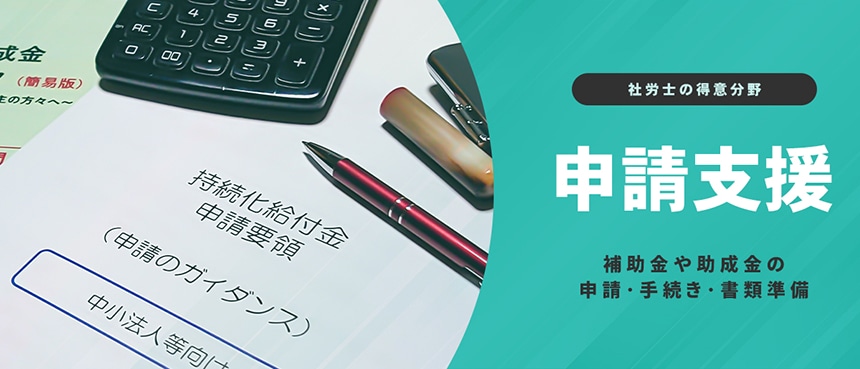
社労士にも補助金・助成金の申請支援として、申請書類の作成や必要な資料の準備、提出手続きの代行を行うケースがあります。
助成金(労働関連に対する厚生労働省が交付するもの)の申請は社会保険労務士の独占業務となっており、申請から交付までを全て任せることが可能です。
行政が交付している補助金については行政書士に依頼するのが一般的ですが、アドバイスや助言が受けられるなど、補助金の種類によっては社労士の方が適任になるケースもあります。
もちろん社労士が行政書士などと連携すれば、より有益なサポートを受けることができます。
⑤メンタルリスク対策
従業員との定期的な面談や年金相談などのサポートも社労士の業務の一つです。
具体的には従業員のメンタルヘルスに関する相談や、職場環境の改善提案、ストレスチェックの実施支援、面談の実施やフォローアップなどを行います。
さらに、年金相談についても社会保険や年金制度に関する専門的なアドバイスや手続きのサポートしています。
従業員が個人的に社労士へ相談できる福利厚生は長く働ける労働環境や安心に繋がり、雇用者・労働者双方にメリットがある施策です。
活用していない企業が多く見られますが、社労士が専門的な知識を活かして支援できる分野ですので検討してみてください。
⑥労務コンサルティング
社労士は労働条件の見直しや働き方改革の提案、労働時間管理、賃金制度の設計、ハラスメント対策、労働法令の遵守支援など、労働環境の改善や適正化に関するコンサルティングを行っています。
一般的な顧問契約の中に含まれているケースが大半ですが、具体的な内容や範囲は契約内容によって異なるため、契約時に労務コンサルティングの範囲や料金について明確に確認しておくようにしてください。
必要に応じて追加のコンサルティングや、専門的なサポートを別途契約するケースもあります。
⑦ADR・労働審判

ADRや労働審判は、弁護士や裁判所の専門家が関与する紛争であり、代理や手続きの進行は弁護士の専門領域です。
ただし社労士は労働関係の法律や制度に詳しく、労働紛争の内容や背景についてアドバイスを行ったり、証拠資料の整理や事前の準備をサポートしたりすることがあります。
紛争に至る前の問題解決や労働条件の改善提案、労働者との交渉支援などの面では社労士の役割が重要です。
そのため、労働紛争そのものの代理や手続きは弁護士の業務ですが、労働問題の予防や事前準備、紛争解決のサポートについては社労士が関わることも多くなっています。
⑧労務デューデリジェンス

労務デューデリジェンス(労務DD)とは、企業の買収や合併や事業再編などの際に、その企業の労務管理や労働環境に関するリスクや問題点を詳細に調査・評価する作業のことです。
M&A時の労務状況チェックなどで社労士の専門性が活きますが、法的な観点や財務的な側面も関わるため、弁護士や会計士、コンサルタントと連携して行うケースがあります。
社労士は労働法令の遵守状況や労働環境の実態把握、労働契約の内容確認などを担当し、リスクの洗い出しや改善提案を行います。
つまり、労務デューデリジェンスの一部または全体を担うことは、社労士の重要な業務のひとつです。
⑨人事関連業務
人事制度・評価制度の設計・運用支援に関してアドバイスを行えます。
賃金体系や評価制度の構築、運用などを通じて、企業の成長を支援してくれる存在です。
人事は基本的に社内で行う業務ですが、人事担当は社労士のサポートを受けることで労務管理や労働法令遵守で質の高い運用を実現できます。
⑩外国人労働者の雇用支援
在留資格の取得・更新手続きのサポートや、労働条件の整備、労務管理のアドバイス、外国人労働者に関する労働法令の遵守支援などを担当します。
初めて外国人労働者を雇用する計画が出た際は、社労士が適切なアドバイスとサポートをしてくれます。
なお、外国人労働者の雇用手続きは社労士の専門分野ではありません。
在留資格の申請や行政手続きの詳細については、行政書士や弁護士と連携して対応するケースが多いです。
社労士の必要性

社労士の主な業務は労働社会保険の手続き代行ですが、他にも補助金申請やメンタルヘルス対策、外国人労働者の雇用支援など多岐にわたる業務を担当できます。
企業のリスク軽減と働きやすい職場づくりに貢献してくれるので、優秀な社労士と顧問契約を結んで各種相談などで有効活用しましょう。
顧問料の安さだけで社労士を選んで最低限の業務しか任せないケースも見られますが、優秀な社労士と顧問契約を結んで上手に活用できれば、企業の健全な成長に大きく貢献してくれます。